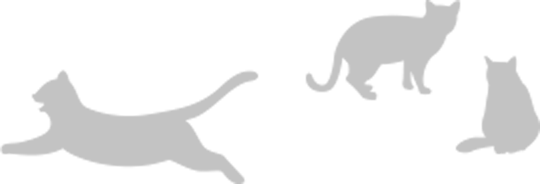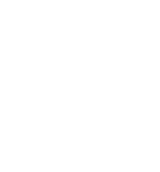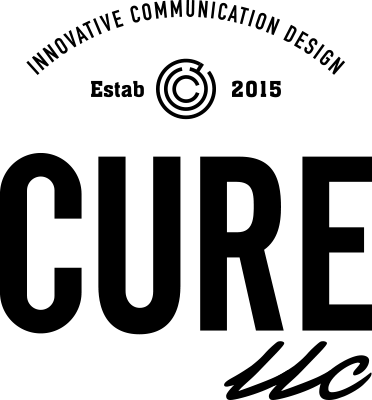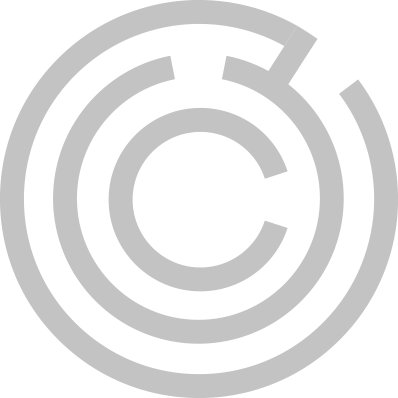はじめに
令和の今、DTPが成熟し、企画・レイアウト・画像処理・校正・入稿までをMac上のデザインアプリで一貫して進めるのが一般的です。PDFプリフライトやカラーマネジメントも日常のワークフローに組み込まれ、制作はスピードと再現性を両立しています。
一方、私がデザイナーとしてキャリアをスタートした広告デザインの現場では、DTPが普及途上で、版下と写植、トンボと罫線——デザイナー自らの手作業が紙面を支えていました。 指先でトンボを合わせ、紙面を設計していた時代です。
広告デザインの現場でも、写植と版下づくりが主役だった90年代初頭でした。
ロットリングのイソグラフ0.1mm〜0.65mm[#1]で罫線を引き、トンボの位置をピンセットで合わせて貼り込み、ペーパーセメント[#2]の独特な匂いを鼻先に感じながら、台紙に文字(写植)やアタリ画像を貼り込んでレイアウトしていきます——。ひとつ一つの工程の積み重ねが、デザインを形にしていきました。
最初にやること/版型→トンボ→基準作図
媒体ごとに版型(仕上がり寸法・塗り足し・のど/小口)が異なるため、まずは指定サイズどおりにトンボを正確に設定します。見開きはのど側の逃げも見込みます。トンボで仕上がり枠を固定したら、内側に製版に影響がでないようにノンフォトブルー[#3]でマージンとグリッドを作図します。ここで基準を決めておくと、後工程の判断が速く、ミスも起こりにくくなります。
文字まわりの設計/写植の指定と入稿準備
まず、見出し・本文などの文字原稿を用意し、経験則を軸にQ数スケール[#6]や歯送りスケール[#7]を使って適切な文字サイズや字間を割り出し、写研の写植見本帳[#8]から書体を選定します。これらの情報をまとめた写植指定紙を作成し、書体/級数(Q数)/文字づめ/文字間隔を明記したうえで、写植屋さんにFAXで依頼します。
当時は文字を画面で直接入力できるわけではなく、外部の写真植字機で出力した紙(=「写植紙」[#4])を受け取り、版下に貼り込む必要がありました。(※本文で便宜的に「活字」と呼ぶことがありますが、実際は写真植字です[#5]。)
版下づくりの実作業/貼り込みとレイアウト
写植紙[#4]は、カッターマット上で不要な余白をデザインカッターで除去し、文字周りに必要なアキだけを確保してから、基準に合わせて台紙に貼り込みます。見出し・本文・キャプションはグリッドと基準線(罫線・トンボ)に沿ってレイアウトします。罫線はイソグラフ、トンボはトンボシールを有効活用して位置の再現性とスピードを両立させます。
固定はペーパーセメントを用い、はみ出したペーパーセメントはラバークリーナー[#9]を軽く転がして除去します。最後に寸法・位置・アキ・禁則処理・体裁を順に確認して仕上げます。
仕上がり安定の要/写植オペレーターさんとのコミュニケーション
指定どおりでも、上がりの字面(じづら)を確認すると微調整が必要になることがあります。行送り、字間、見出し前後のアキ、ルビ位置などを具体的な数値と意図を添えて再指示し、再出力を依頼します。こうした版下完成までの往復が、読みやすさと仕上がりの安定を担保しました。
また、写植オペレーターのセンスに助けられる場面も少なくありませんでした。こちらがQ数と行送りを指示するだけで、ベタ打ちでも癖の少ない美しい箱組に仕上げてくださり、後工程の微修正が減り、戻し回数の抑制にもつながりました。
製版指定/色指定とオーバーレイ指示(CMYK/特色)
版下の制作が完了したら、次は製版指定です。 台紙の上にトレーシングペーパー(オーバーレイ)[#10]を重ね、写真・ベタ面・罫線・文字・背景ごとに色指定と加工指定を書き込みます。版下自体を汚さないよう、指示はトレーシングペーパー側に集約します。
– CMYKの指定
写真や色面にはCMYK配合(例:C70 M20 Y0 K0)や網点濃度(アミ%)、必要に応じてスクリーン線数(lpi)を記します[#11]。背景色面も同様に配合とアミ%を明記し、重なり順を注記します。
– 特色(スポットカラー)の指定
コーポレートカラーなど再現性重視の箇所はDIC/TOYO/PANTONEで特色番号を指示します[#11]。またノセ(オーバープリント)/ヌキ(ノックアウト)などの刷り指定も併記します[#12]。
– 重なり・抜き・トラッピング
版ズレ対策としてノセ/ヌキを明示し、必要に応じてトラッピングの有無や方向を指定します[#12]。細線や小サイズ文字はスミノセで沈みを防ぐ指示をすることもあります。
– 写真の指示
トリミング位置、ハイライト/シャドウの目安、背景との色なじみの方向性など、製版オペレーター向けの注記を記します。最終の色確認は校正紙で行う前提です。
色指定は、基本的には頭の中の配色設計を土台に組み立てますが、 とりわけグレーは配合や重なり、隣接色との関係でわずかな深みや発色の違いが生じます。そこで、大日本インキ化学(DIC)のカラーチャート[#13]を机上に広げ、近似トーンを当てながら周辺色とのバランスをチェックし、必要に応じて特色番号またはCMYK配合へ落とし込みました。紙の白色度や印刷条件で見え方が変わる前提で、最終判断は実物チャートと校正紙で確認します。
アナログ制作で培った「頭の中の仕上がりイメージ」
アナログ制作では、仕上がりイメージを実際に確認できるのは校正紙を出稿したときだけでした。 ゆえに、工程の途中では画面に頼らず頭の中で仕上がりイメージを組み立てる力が自然と養われました。この蓄積はDTP中心の現在でも生きています。ラフ作成では完成形から逆算して構図・文字組み・余白の配分を素早く決められ、修正提案や方向転換にもスピード感を持って対応できます。 さらに、連携するグラフィックデザイナーやウェブデザイナーとも意図と根拠を共通言語で共有し、イメージの齟齬を最小化。仕上がりイメージをチームで明確に揃えます。
私が体験したアナログとDTPの端境期とは…
私がデザイナーとしてキャリアをスタートしたのは、アナログとDTPが入れ替わる90年代初頭でした。最初の3年間はアナログ実務が中心で、トンボの正確な設定、ノンフォトブルーでの基準作図、イソグラフでの罫線、写植とアタリ画像の貼り込み――「版型→基準→段取り」の手順が当たり前の流儀として身につきました。
一方、勤めていた広告代理店では1992年ごろに最初の1台のMacintosh(DTP環境)が導入され、その後は段階的に台数が増え、しばらくはアナログとDTPが併走しました。版型やグリッドの設計思想はそのままに、レイアウトと出力検証だけをDTP側へ置き換えていった時期です。業界全体としては90年代中期にDTPが主流となり、写植・版下は徐々に役割を終えていきました。
当時は写植屋さんとの往復に一定の時間がかかりました。指定はFAXで送付し、写植紙の出力が完了したら連絡を受け次第、もっぱら自転車で引き取りに向かいました。受け取り後は字面の確認や仕上がりの校正を行い、版下制作から製版指定へと工程を進めつつ、その最中にも別案件の各社から上がってくる色校正紙のチェックや戻し指示など、複数タスクを同時に進行していました。現在はDTPが主流となり、これら一連の作業は席にいながら短時間で対応できるようになり、生産性は大幅に向上しています。
デザインの骨格は「基準」と「段取り」
罫線・トンボ・グリッドで基準を先に定め、重要度の高い要素から段取りを組んで配置する。
これにより判断のブレが減り、修正も迅速になる。
◎ 基準が明確だと、ディテールの詰めが的確になる。
◎ 余白は「何もない」ではなく、読みを導く要素として機能する。
◎ 目の動線は、線・余白・文字量の整合で決まる。
【注釈】
#1 イソグラフ
ロットリングの製図用ペンです。一定の線幅を保てる構造で、番手(例:0.10〜0.65mm)を使い分けて罫線や基準線を引きます。
#2 ペーパーセメント
ゴム系のり(ラバーセメント)です。貼り直しを前提に使え、乾燥後はまとまって除去しやすく、版下の貼り込みに用います。
#3 ノンフォトブルー(ノンリプロブルー)
製版に影響がでないように設計された淡い青の筆記色です。版下ではマージンやグリッド、指示メモの下書きに用います。デジタル取り込み時は、青成分の除去やレベル補正で目立たなくできます。
#4 写植紙
写真植字機で出力した文字を感光紙(印画紙)に焼き付けた紙片。指定した書体・級数(Q数)・字間・行送りで長尺出力ができ、断裁して版下に貼り込みます。表面は半光沢〜光沢で、湿気でカールしやすいため貼り込み時は注意が必要です。
#5 写真植字(写植)と活字の違い
本文で「活字」と表現していますが、実際は金属活字ではなく、専用機で感光紙に文字を焼き付ける写真植字が主流でした。
#6 Q数スケール
写植時代に文字サイズ(級数)を決めるための定規。Q(1Q=0.25mm)を目盛りとし、見出し・本文のサイズ設計に用います。
#7 歯送りスケール
写植時代の字送り・字間を見積もるためのスケール。ベタ/トジ/アキの度合いを定量化し、段落の読みやすさを調整します。
#8 写研の写植見本帳
当時主流だった写研フォントの書体見本集。書体名・太さ・かなの表情などを視認し、適切な級数や行送りの目安とともに選定します。
#9 ラバークリーナー
ラバーセメント用のクリーナー(ピックアップ)です。乾いたペーパーセメントの余剰を、消しゴム状の塊で転がして取り除く道具です。
#10 トレーシングペーパー(オーバーレイ)
版下台紙に重ねて色指定・加工指定を書く薄紙。版下を汚さずに指示を集約でき、トンボ位置で合わせてホチキス留めやテープ留めにして運用します。
#11 CMYK/特色
CMYKはインキ4色(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)の配合指定。アミ%やスクリーン線数(lpi)を併記する場合もあります。特色はDIC/TOYO/PANTONEなどの単独インキ指定で、再現性が高いのが利点です。
#12 ノセ/ヌキ/トラッピング
ノセ(オーバープリント)は下の版の上に重ね刷り、ヌキ(ノックアウト)は下地を抜いて刷る指定。トラッピングは見当ズレを吸収するための版のわずかな重ねのこと。小サイズの文字や細線ではスミノセが用いられることがあります。
#13 DICカラーチャート
大日本インキ化学(現DIC)の色票。特色番号と近似CMYKを確認したり、隣接色とのバランス検証に用います。最終判断は実物チャートと校正紙で行います。
東京でパンフレット/プロモーションツール制作をご検討中の方へ
東京都内は対面orオンライン、全国はオンラインで対応いたします。版下時代からの経験を基に、ブランドのトーン&マナーを守りながら、可読性と美しさを両立する印刷物を——文字組みと余白の基準から一貫設計でご提案いたします。
お問い合わせはこちらよりお願い致します。 → お問い合わせフォームへ
お気軽にお問合せください。
RELATEDPOSTS